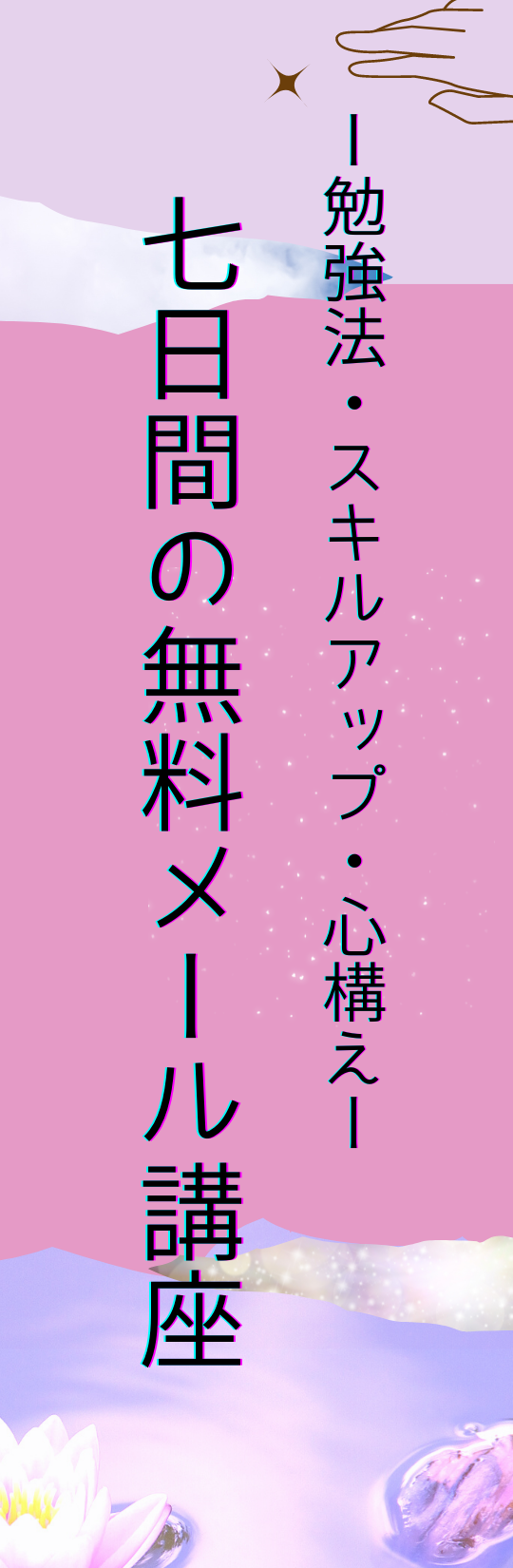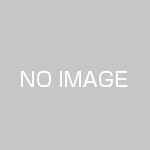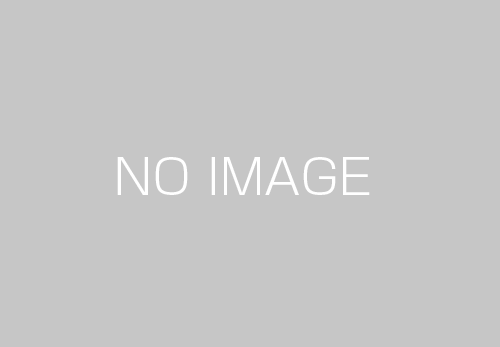こんにちは。
采慧(サキ)です。
今日のスキルアップ情報は
先週お届けした「師匠に勧められた本」
へのご感想とご質問にお答えします。
まずは、コメントをご紹介します。
——————————————–
<ご感想&ご質問>
サキ先生お久しぶりです。
春休みの今、家族みんな、
まとまった時間ができたので
さっそく中学のプリントや教科書などを
整理や処分してきれいにしました。
教科書ってほんとうに勉強になりますし
おもしろいです。
天体もキレイな写真が載っていました。
小惑星のケレスなども。
ひとつ気づいたこと
「すいせい」と聞くと
占星学を学んでいる自分は
「水星」をイメージするけど、
ほうき星と呼ばれる「すい星」
こちらもありますね。
占星学では、こちらの「すい星」も
研究されたりしているのかな?
と疑問に思いました。
(原文ママ一部抜粋)
——————————————–
K.Y.さん、近況報告と併せて
いつも興味深いご質問を頂き
ありがとうございます。
占星学の知識を得てから
学生時代に習った天文の復習をしたり
最近の子供たちの学習内容を見ると
本当に勉強になることばかりで
つい引き込まれてしまいますよね。
さて、ご質問頂いた
彗星の占星学研究は
大昔から行われていたようです。
世界中で、紀元前の彗星の記録が
見つかっているようですが
占星学の発祥地メソポタミアの
彗星の出現記録も残されています。
古代エジプトでは
暦などを作成する目的で
天体観測をしていたため
規則的に繰り返し起こる
天文現象に注目していて
日食、月食、彗星、惑星の運行
などの記録は殆どないようです。
対照的に、メソポタミアでは
それら全ての記録が
詳細に残されています。
その理由は
天空上の変化を見ることで
占いをしていたからです。
これが占星学の始まりです。
天空の世界と地球上の出来事に
相関があると考えていたため
星の動き、天界の変化と共に
その時地上で起きた出来事も
記録していました。
とても近い地域で
共に同じ星空を見つめながら
それぞれに着目点が違い
天体観測によって得られた成果も
違うことは、興味深いですよね。
現在の占星学では、主に
太陽系の太陽と惑星、準惑星、
小惑星などの動きによって
出来事を予測するスタイルですが
占星学の世界で
小惑星に分類されているキロンは
天文学では、彗星と小惑星の
両方に属していますので
天文学的に言えば、占星学では
現在も彗星を使って占っている
と言うこともできそうです。
参考になりましたでしょうか。
あなたのご感想やご質問も
メルマガに登録してお気軽にお寄せ下さいね。
◇◇◇
次回のスキルアップ情報は
占星学講座の募集案内を
お届けする予定です。
どうぞお楽しみに。